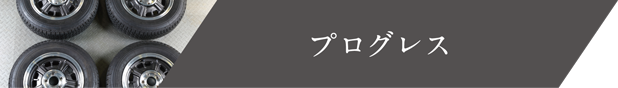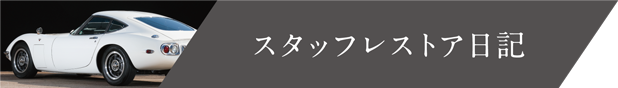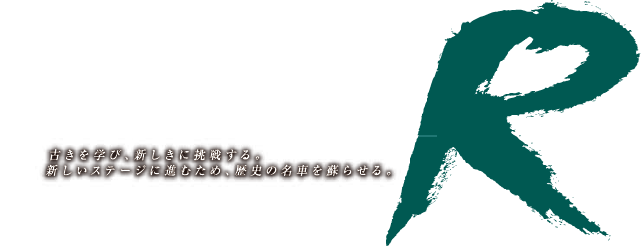

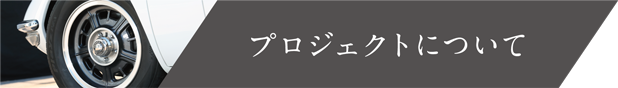
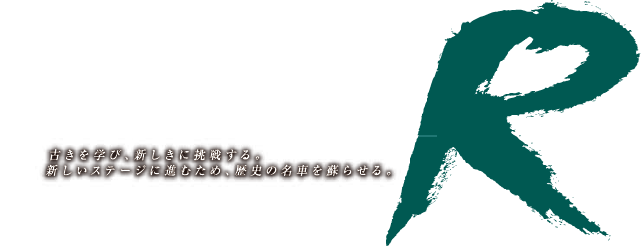
かつて存在した歴史に名を残す名車と言われた車が存在する。
しかし、年月はその名車を世の中から消し去ろうとする。
それらを過去のものとして忘れ去ることは今ある技術の礎を捨て去ることでもある。
大阪トヨペットグループでは、2015年、トヨペットコロナを修復した経験を持ち、その時の経験から歴史の財産である名車たちをあらためて見直し、蘇らせることにチャレンジすることで、技術力に大きな知的財産としてのバックボーンを与えてくれると感じることができた。
かつての名車を「復活(Revival)」させ、当時の形に「生き返らせる(Restore)」。
そして完成度の高い状態で「自動車競技(Rally)」に出場する。
それにより技術力を「高める(Raise)」ことができる。
同時に1つの目標に全社員が一丸となることで社員と社員の「絆(Relationship)」を築き、同時にモータリゼーション社会の中でクルマを愛する人々の「絆(Relationship)」に貢献できる。
5つの“R”を実践する新たな挑戦へのプロジェクト「プロジェクトR」を、エンジニア技術研修の一環として、新たな教育プログラムを設定。
日本の世界の歴史的財産を守り後世に伝えると共に、大阪トヨペットグループの店舗では、お客様が大切にする思い出の愛車をいつまでも輝き続ける事ができるお手伝いを行う整備責任を果たしていきたい。







下の動画は1989年、ヨーロッパで開催された、7日間約3000kmを走破する、ピレリークラッシックマラソンというラリーの映像です。
ドライバーは1970年代、セリカやレビンでWRCラリーに出場、幾度となく優勝し、「ラリーの神様」と呼ばれ、ドライバーの引退後はトヨタ・チーム・ヨーロッパの監督として、トヨタF1の代表を務めるなど、生涯トヨタと共にモータースポーツの発展に努めた人物。オベ・アンダーソンです。
そのオベ・アンダーソンがドライブし、ピレリークラッシックマラソンに出場した、歴史ある2000GTを自社エンジニアが再生させることで、クルマの基礎から自動車を学び直し、同時にレストアという新しい取り組みにチャレンジをします。